放射線科
放射線科(診断)
国立病院機構相模原病院放射線科では、以下の検査・治療を行うことができます。
一般撮影

“一般撮影”とは、あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、健康診断での胸の写真や骨折した時に撮影する体の骨の写真などのいわゆる“レントゲン写真”のことです。
一般撮影はエックス線を用いて身体の診たい場所を二次元的に写し出しています。
エックス線が照射され体内に入ると、透過して体外に出てくるものと、体内で吸収されるものとに分かれ、エックス線が透過した部分は黒、吸収された部分は白く表されます。
その透過・吸収の差を白から黒の濃淡の変化で骨や内臓といった内部構造を映し出しているのがエックス線写真です。手足や背骨等の骨の写真では、骨の形状把握や骨折の有無・度合いから治療方針を決定したり、撮影した写真を基に手術のための計画に用いたりします。
胸部写真では、肺炎や結核、気胸などの肺疾患の評価から、血管や気管支の形態評価など多岐にわたり、心疾患などの多くの病態の鑑別に不可欠な検査となります。また、腹部写真では、胃や腸管内のガスや便のたまり具合、胆石や尿路の結石、腹水の有無などの疾患のほか、腰椎や骨盤の変形などがわかることもあります。
検査時には、診療放射線技師から様々な決められた体位を取る事をお願いしています。
診たい部位を最適に写し出すためとご理解いただき、ご協力のほど宜しくお願い致します。
一般撮影前の準備
一般撮影では、プラスチック(ボタン)や金属(ファスナー)、洋服の模様などが写ります。これらは診断の妨げになる恐れがございますので、検査着に着替えていただく場合がございます。また、時計やネックレス等の貴金属類の他、湿布や使い捨てカイロも同様に写り込んでしまいますので外して下さい。
一般撮影での注意事項
一般撮影は普通のカメラで写真を撮るのと同じで、動いてしまうと写真がブレてしまい、小さな病変を見落とす原因になってしまうことがございます。呼吸や体の動きによるブレを抑えるため、息を止めて撮影を行う場合がございますので担当技師の指示通りにお願いいたします。
マンモグラフィ

“マンモグラフィ”とは、X線を使って乳房の撮影をする乳房専用の検査です。マンモグラフィを撮影することで、視触診では分からなかった早期の乳がんを発見できることがございます。また、触れるしこりが良性であるのか悪性であるのかの鑑別にも有用です。
マンモグラフィの撮影方法
マンモグラフィは左右の乳房を比較することが重要であるため、通常両側の乳房をそれぞれ2方向から撮影します。検査時間は両側撮影で20分程度です。
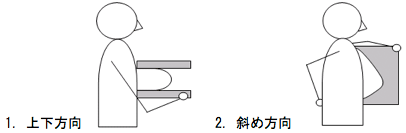
骨密度測定
“骨密度測定”とは、骨密度(骨が“スカスカ”になっていないかどうか)を測定する検査です。
国立病院機構相模原病院での骨密度測定の特徴

国立病院機構相模原病院では、X線を用いることにより、筋肉や脂肪などの厚みに関係なく骨の成分だけを抽出して測定する方法を採用しております。従って、体格などに左右されず、いつも安定した測定値を得ることが可能です。主に骨粗しょう症の診断に用いられる検査です。
国立病院機構相模原病院では、腰椎正面、大腿骨頚部の骨密度を測定しております。腰椎正面や大腿骨頚部は、骨粗しょう症による骨折が生じやすい部位であり、その当該部位を測定することで、最も正確に骨の状態を評価する事ができます。検査時間は測定する部位によって異なりますが、通常5~20分です。
検査前の準備
- 骨密度測定は、食事制限や水分摂取の禁止などはございません。
- 検査当日はボタンや金具等がない服装でお越し下さい。(女性の方でブラジャーをされている方は留め具が測定の妨げになる場合がございますので、検査前に検査着に着替えていただきます。)
- 湿布や使い捨てカイロ等は検査前に外して下さい。
- 胃や腸のバリウム検査、CT、血管撮影などの造影検査、放射線同位元素を使用したRI検査の後に骨塩測定検査を行うと、測定部位にお薬が重なって測定値を過大評価してしまう 恐れがございますので、検査担当者にお伝え下さい。
検査中の注意事項
- 検査中は検査台が上下左右に動きますので、身体を動かすと大変危険です。 また身体を動かしてしまうと画像がぶれて測定結果に支障がでますので、身体を動かさないようお願いいたします。
- 呼吸は普段通りにしていただいて構いません。リラックスして検査をお受け下さい。
透視検査

当院では、X線を用いて体内の様子をリアルタイムで観察できる「X線透視装置」を導入しています。X線透視検査では、さまざまな検査や治療を行うことができます。
造影剤を使用した検査
多くのX線透視検査では、「造影剤」と呼ばれるX線が通過しにくい液体を使用します。造影剤を体内に投与することで、造影剤は画像上では黒くなり、画像上でのコントラストを観察することで臓器や組織の形状や機能を詳しく評価することが可能です。
主なX線透視検査のご案内
・内視鏡を用いた胆管検査
胆汁の流れが障害されると、黄疸や腹痛などの症状が現れることがあります。当院では、X線透視画像で確認しながら内視鏡を胆管まで進め、造影剤を使用して狭窄部位やその原因を調べます。必要に応じて、狭窄部位にステントを挿入する治療も同時に行うことが可能です。
・上部消化管造影検査
バリウムなどの造影剤を服用していただき、食道・胃・十二指腸・小腸の形や粘膜の状態、通過の様子を観察します。検査台の上で体の向きを変えながら、さまざまな方向から撮影を行います。
・下部消化管造影検査
小腸や大腸が閉塞した状態(腸閉塞・イレウス)の場合、イレウスチューブと呼ばれる長いチューブをX線透視画像で確認しながら下部消化管に挿入し、状態の改善を図る治療を行います。
・神経根ブロック
神経組織の障害による痛みやしびれを緩和するため、局所麻酔やステロイド剤を用いる治療法です。必要に応じて、ヨード造影剤を使用して神経根の位置を確認しながら処置を行います。
透視検査の注意事項
上部・下部消化管検査において、非常に重要なのが検査前の準備(前処置)です。胃や大腸に食物が残っている状態で検査を行いますと病気が食物に隠れてしまったり、食物が病気に見えたりすることがございます。質の高い検査および診断を行うためには、検査前の準備をしっかりしていただくようお願いいたします。
血管造影(検査・治療)

IVR(画像下治療・放射線カテーテル治療)は、体に負担の少ない治療法です。細いカテーテル(管)や針を使用し、レントゲンやCTなどの画像を見ながら正確に治療を行います。お子様からご高齢の方まで、全身の様々な病気に対応できる治療法として、現在多くの医療現場で選ばれています。
がん治療、血管の病気、お腹の臓器の疾患、緊急時の治療など幅広い分野で活用されており、患者様にとって重要な治療選択肢の一つとなっています。従来の外科手術と比べて体への負担が軽く、回復も早いという特徴があります。
がん治療への取り組み
・肝細胞がんの治療
肝細胞がんに対しては、肝動脈化学塞栓術(TACE)という効果的な治療を行っています。この治療は、手術が難しい患者様に対する標準的な局所治療として広く認められています。
治療では、足の付け根などからカテーテルを挿入し、肝臓の動脈まで慎重に進めます。そして、がん細胞に栄養を送る血管に抗がん剤を直接注入し、同時に血管を詰めることで、がん細胞への栄養供給を遮断し治療効果を高めます。
血管系疾患の治療
・動脈瘤の治療
内臓動脈瘤・末梢動脈瘤(腎動脈瘤、脾動脈瘤、肝動脈瘤、腸間膜動脈瘤など)は、動脈硬化や血流の変化が原因で血管にこぶのような膨らみができる病気です。
部位や瘤の大きさにもよりますが、予防的な治療を行うこともあります。
・動静脈奇形(AVM)の治療
動静脈奇形(AVM)は、全身の様々な部位に発生する可能性がある、先天性または後天性の血管の異常です。当科では脳以外の動静脈奇形に対する血管内治療を専門的に行っています。
肺動静脈奇形(PAVM)では、チアノーゼ(皮膚や唇が青くなる症状)や脳梗塞・膿瘍の原因となる可能性があります。当院では、体に負担の少ないコイル塞栓術による治療を実施しており、外科的切除と同等の効果が期待できます。
腎動静脈奇形では、腎出血や血尿、心不全のリスクがあるため、カテーテルを腎動脈まで進めて液体塞栓物質やコイルで安全に閉塞させる治療を行います。骨盤部などその他の部位のAVMについても同様の方法で塞栓術を実施し、症状の改善や破裂予防に取り組んでいます。
・静脈奇形の治療
先天的な静脈奇形(静脈性血管奇形)に対しては、硬化療法(硬化剤注入)や塞栓術などの治療法を提供しています。
・CVポート造設
CVポート(皮下埋め込み型中心静脈アクセスポート)とは、中心静脈カテーテルの一部で、抗がん剤や高カロリー輸液の投与に使用します。IVHカテーテル(中心静脈カテーテル)と違い、末梢を直径2~3cmのリザーバータンク(ポート)に接続し、外科的処置にて皮下に埋没させます。血管刺激性の強い薬剤を末梢血管から投与した場合、血管炎、腫脹や疼痛などが起こることがありますが、CVポートのカテーテルは中心静脈に挿入されているため、これらの血管刺激性に影響されることなく、安定的な持続的投与が可能で、入浴や日常動作にも制限がありません。
・画像ガイド下生検
CTやエコーで病変を確認しながら組織を採取。これにより開腹せずに確定診断に必要な組織標本が得られ、迅速な診断と治療方針の決定に繋げます。
・膿瘍・嚢胞ドレナージ
肝膿瘍や腎膿瘍、膵仮性嚢胞など液体が溜まった病変には経皮的ドレナージを行います。局所麻酔下に皮膚から患部へドレーン管を留置し膿や液体を体外に排出することで、感染のコントロールや症状の改善を図ります。外科的ドレナージに比べ侵襲が小さく、全身状態の悪い患者様にも安全に施行できます。
患者様へのメッセージ
当院のX線透視検査及びIVR部門は患者様の体への負担を最小限に抑えながら、効果的な治療を行うことで、患者様の生活の質の向上を目指しています。
検査等に関するご不明な点やご心配事がございましたら、いつでもお気軽に医療スタッフにご相談ください。私たちは患者様とそのご家族の皆様に寄り添い、安心して検査や治療を受けていただけるよう全力でサポートいたします。
血管造影検査・治療の注意事項
- 動脈に針を刺しますので検査中は身体を絶対に動かさないで下さい。万が一、かゆみがあったり、汗を拭きたかったりする場合には、看護師が常時付き添っておりますのでお申しつけ下さい。
- 動脈にカテーテルを挿入しておりますので、検査後は医師の指示があるまで絶対安静となります。
CT検査

CT(コンピュータ断層撮影)検査はX線を使用して体の輪切り像を撮影し、体の内部を精密に調べられる検査です。全身における全ての疾患が対象で、検査時間は検査内容により異なりますが5分~20分程度です。輪切りの画像を利用して様々な方向の画像や、3D画像を作成して診断に役立てています。
検査方法
CT検査には、2種類の方法がございます。
単純CT検査:造影剤という薬を 使用しないで 撮影を行う方法
造影CT検査:造影剤という薬を 静脈注射して 撮影を行う方法
症状や病状によって造影剤を使用する場合があります。造影剤の使用により、質の高い診断(より正確な診断)が可能となります。
造影CT検査について
造影CT検査ではヨード造影剤を静脈内に注入します。注入時体が熱く感じることがありますが正常な反応ですので心配ありません。体内に入った造影剤は腎臓から尿中に排泄されます。
ヨードアレルギーのある方、喘息の既往のある方、腎機能の悪い方など造影剤が使用できない場合がありますので、あらかじめご相談ください。
ヨード造影剤は安全な薬剤ですが、まれに副作用が起こることがあります。当院では万が一の副作用に対して万全の体制を整えて検査を行っています。より安全な検査を行うため検査前に問診票などのご記入をお願いしております。
MRI検査

MRIとはMagnetic Resonance Imaging の略で磁気共鳴画像撮像法のことを言います。この検査は強力な磁場と電波を利用して体内にある水素原子から出される信号を高解像度の画像として変換して表示しています。CT検査など放射線科で取り扱う他の検査や治療と異なり放射線は使っていないため放射線による被ばくの心配はありません。患者さんには強力な磁場が発生しているトンネル状の装置の中に撮像する部位に応じた専用の器具を装着していただき防音のためのヘッドホン等をつけていただいた状態で入っていただきます。撮像する部位によっては息を止めていただく等の協力をしていただくこともありますが、頭部・脊柱・各種関節などは基本的には寝ているだけの検査となります。検査時間は15分~60分程度と検査する部位によって異なります。
国立病院機構相模原病院でのMRI検査の特徴
当院ではMRI装置が2台(SIEMENSE社製3.0T・PHILIPS社製1.5T)稼働しております。3.0Tの導入により、肝臓の弾性率分布を非侵襲的に測定が可能になる等、多様な検査に対応できるようになりました。頭部から足部まで各部位ごとにはなりますが全身の検査に対応しております。また、不随意運動などで体の静止が難しい方の頭部検査などには体動補正等をおこなう撮像も可能であります。
MRI検査時のお願い
- MRI検査室は、金属を持ち込むと大変危険です。安全を確保するため、毎回チェックシートへの記入をお願いしております。また、金属探知器による確認をさせていただく場合もございます。
- MRI検査は、検査中に大きな音が鳴りますので、ヘッドホンや耳栓などで防音措置を行います。
- 予約検査とは別に緊急検査が入ることがございます。検査時間に遅れが出る場合もございますので、予めご了承願います。
- 緊急用ブザーをお渡ししますので、検査中に何かございましたら緊急用ブザーで担当技師をお呼び下さい。
RI検査(核医学検査)

“核医学検査”とは、放射線を放出する放射性同位元素を含んだ薬(放射性医薬品)を、注射などによって体内に投与し、特定の臓器や病変部に取り込まれた薬から放出される微量の放射線を、体外のカメラで検出し、画像にする検査です。
全国で約1600もの病院(施設)で施行されている、安全の確立された検査となっております。
国立病院機構相模原病院でのRI検査の特徴 その1
国立病院機構相模原病院では、2025年6月より、最新のSPECT/CT装置を導入いたしました。
SPECT/CT装置は、核医学検査装置とCTが一体となった装置です。CTを併用する事により、より解剖学的な位置の同定が可能となります。

核医学画像の機能情報とCT画像の形態情報が組み合わさる事により、容易に集積部位を同定することが可能になります。また、SPECT/CT融合画像は患者さまにも、病態を容易にご理解いただけると思います。
| ・骨シンチ ・腫瘍・炎症シンチ(Gaシンチ) ・胃所性胃粘膜シンチ ・脳血流シンチ ・心筋ピロリン酸シンチ |
・副甲状腺シンチ ・副腎髄質シンチ ・DAT(ドパミントランスポータ)シンチ ・肺血流シンチ |
・消化管出血シンチ ・甲状腺(Tc)シンチ ・ソマトスタチン受容体シンチ |
国立病院機構相模原病院でのRI検査の特徴 その2
国立病院機構相模原病院では、心筋血流シンチ(Tc-99m)検査を短時間で行うことができます。心筋血流シンチ(Tc-99m)検査は、低侵襲に心筋虚血を評価する事ができますが、撮影時間が長いという問題がございました。これに対し、国立病院機構相模原病院では、心臓専用の撮影を使用する事により、従来のおよそ半分の時間にて検査が行えるようになりました。
検査前の注意事項
検査の種類によっては、前処置(前もっての準備)が必要なものがございます。例えば、食事制限をしていただいたり下剤を飲んでいただいたりと、その方法は様々です。検査の予約をする際に、その検査に対する前処置について担当医もしくは担当看護師から説明がございます。
診断部門スタッフ紹介
| 統括診療部放射線科部長 | 瀧川 政和 | 日本医学放射線学会 放射線診断専門医 日本インターベンショナルラジオロジー(IVR)学会 専門医 |
|---|---|---|
| 統括診療部放射線科医長 | 大森 智子 | 日本医学放射線学会 放射線診断専門医 日本核医学会 核医学専門医 日本インターベンショナルラジオロジー(IVR)学会 専門医 |
| 統括診療部放射線科医長 | 平川 耕大 | 日本医学放射線学会 放射線診断専門医 日本核医学会 核医学専門医 |
| 統括診療部放射線科医師 | 浅野 雄二 | 日本医学放射線学会 放射線診断専門医・認定研修指導者 日本核医学会 核医学専門医 日本核医学学会 PET核医学認定医 |
| 統括診療部放射線科医師 | 井上 登士郎 | 日本医学放射線学会 放射線診断専門医 |
放射線科(治療)
放射線治療

放射線治療は、がんに放射線を照射することで腫瘍の縮小や消失を期待する治療法です。手術と同様に、特定の部位に対して行う「局所治療」に分類されます。たとえ転移がある場合でも、症状の緩和を目的として照射を行うことが可能です。たとえば、骨転移による痛みや、腫瘍からの出血に対する止血目的の照射などが挙げられます。
当院では、リニアック(直線加速器)を使用して高エネルギーのエックス線や電子線を発生させ、体の外から照射します。これらの放射線は、がん細胞の遺伝子に損傷を与えることで、がん細胞を死滅させる効果があります。1回の治療時間はおおよそ10分程度で、痛みや熱さを感じることはありません。この照射を平日のみ、毎日行います。
治療期間は、がんの種類や照射部位によって異なります。たとえば前立腺がんの場合は約2か月、乳がんの場合は4〜6週間程度を要します。副作用については照射部位によって異なりますので、診察時に詳しくご説明いたします。
当院では、IGRT(画像誘導放射線治療)機能を備えており、より正確な位置合わせが可能です。そのため、治療効果の向上や副作用の軽減が期待できます。多くの患者さんは通院での治療が可能であり、ご高齢の方にも治療を受けていただけます。
受診される方
予約制で担当医の紹介状が必要です。
初めの診察で放射線治療の適応を確認し、照射方法、副作用について説明させていただきます。
納得され同意が頂ければその後治療計画CTを行い、後日照射開始となります。
照射期間中は放射線科でも定期的に診察し、副作用の程度を確認させていただきます。
分からないことがあれば診察時に何でもご質問下さい。
対象となる疾患
前立腺がん、乳がん、肺がん、脳腫瘍、咽頭がん、喉頭がん、食道がん、直腸がん、子宮がんなど。
各種がんの再発、骨転移、リンパ節転移、脳転移。当院では前立腺がんや乳がんの患者さんが多いです。
特色
当院では画像誘導放射線治療(IGRT : image-guided radiotherapy)が可能です。
照射を行う直前に、治療装置上で撮影した画像を利用して照射部位の微調整を行います。
この技術により高精度の位置合わせが可能になり、治療効果の向上や副作用の軽減が期待できます。
ストロンチウムや塩化ラジウムによる骨転移の治療も可能です。
IMRT、定位照射、小線源治療は行っていません。
治療部門スタッフ紹介
| 放射線科医長 | 北野 雅史 | 日本医学放射線学会 放射線治療専門医 |
|---|---|---|
| 統括診療部放射線科医師 | 飼沼 卓朗 |